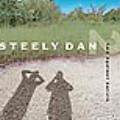
TWO AGAINST NATURE 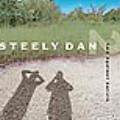
いよいよ20年ぶりに新譜が発売されました。日本のFM局でもヘビーローテーション、なかなか評判も良く、また売れ行きも好評だそうです。とりあえず、曲別に個人的な感想を書いてみました。
1. Gaslighting Abbie
のっけからファンキーなリズム、シャープなギター+ホーン、そこにFAGENのヴォーカル、紛れもない、S.D.サウンド。待ちに待った、新作なのだ、という思いがよぎる。お約束の女性コーラス隊、ホーンセクションもこざっぱりまとまっている。KAMAKIRIADに近い作風。曲順は適当でも、オープニング曲だけはよく考えて決める、という二人の意図は一応成功した様子。
2. What A Shame About Me
ラジオで数回聴いた事があったのであまり感激しなかったものの、バランスがいいというか、今の時点で一番気に入ってる曲。出だしの部分はSTEVE WINWOODの"Roll With It"を思い出してしまったが、ギターソロなど、曲の展開具合がAJAの作風に近いのでは?ブルージーなギターは全てベッカー。肝心のサビの部分が字余りなのが少し気になる。後半のトランペットが面白い。1st シングルとはいえ、シングル盤は出てないらしい。
3. Two Against Nature
なんとも実験的な曲。ボッサなリズムにうねるベースライン。しかも、特に大きな展開もなくそのまま終わる感じ。よく聴くと、様々な音が挿入されている。正直言って(今のところ)、あまり好きになれない。入れない方が良かったような。でもタイトル曲だしなあ…
4. Janie Runaway
どこかで聴いたようなリズムパターン。"Daddy Don't Live 〜"だろうか。またしてもサビの部分が字余りなのが…。
歌詞には、GRAMACY PARKから、DEAN AND DELUCA(N.Y.一有名なデリ&スーパー)まで登場するのには驚かされた。
5. Almost Gothic
最も雰囲気のいい曲だが、どこか、不完全燃焼な感じ。この曲も肝心のサビが曲を台無しにしていると思う。よく聴くと"Deacon Blues"を彷彿させ、なかなか良い展開なのだけど。
(この曲に限らず)水中で聞こえるような音?も少し気になる。
6. Jack Of Speed
期待してただけに一番がっかりした曲。96年の来日公演でBECKERが歌ったヴァージョンは、よりアグレッシブで迫力があったから。このヴァージョンも上品にまとまってるので悪くないのだが、元(96年)ヴァージョンの完全版を先に聴きたかった。そのヴァージョンではホーンだけだったオープニングにギターを重ねるなど、斬新なアレンジという印象を受けたものの、もっとパワフルな展開が合う曲のはず。ちなみに、歌詞も大分変わっている。とか言いながら、基本的にかっこいい曲である事は確か。
7. Cousin Dupree
今までこれほどポップな曲があっただろうか? ウエストコーストロックのような軽快なノリ。ハッキリ言って意外な曲だった。恐らくライブで演奏するのを想定して書かれた曲なのだろう。96年の北米公演で披露された、"Wet Side Story"にリズムパターンが似てるので、それを土台に書き直したのでは?
8. Negative Girl
凝った構成はいかにもS.D.らしい作品。完成度ではピカイチ。ここではわりと有名なミュージシャンがクレジットされている。D.PARKS、V.COLAIUTAなど。エンディングで少し見せ場?はあるものの、華麗なソロプレイがないのは寂しい。フェイゲンの声の衰えも気になる。無理な声域の曲はやらない方針だったはずだが…。
9. West Of Hollywood
なかなかよくできた曲。メロディーもキャッチーだし、歌詞とのバランスもいい。少々余計な音が多い感じはするが。珍しくSAXソロがフィーチャーされているが、はっきりいって長すぎるんじゃ? ソロがアクセントになってない。「ラストの曲だし、残りの時間が余ったから好きなようにやっていいよ」、って感じ、と言ったら言い過ぎか?
殆どのリスナーはSTEELY DANの新譜=後期S.D.サウンドの再現を期待したはず。
かくいう自分も一応は2000年代のAJAを期待していたが、恐らくそれは叶わない事だろうと思っていた。そんなわけで、最初に聴いた時は、なんだかホッとした反面、少し物足りない印象を受けた。確かに少し聴いただけでS.D.とわかる音ではあるものの、これまでの作品とは確かに違っている。では後期の作品(特にGAUCHO)との違いはどこにあるのか?
結論から言えば、S.D.サウンドの特徴 ―複雑でわかりにくい曲でも、(毒を含んだ歌詞と)甘美でキャッチーなメロディーが共存していた―、が今作ではキャッチーで美しいメロディーが足りてない、という事ではないだろうか?
歌詞はBECKERに負う部分が大きいことは本人達も認めているが、二人のコラボレーションという事で、BECKERを強調する事に固執し過ぎたのか、はたまたメロディーのアイディアが枯渇気味なのか?
気になったのは、どうもしっくり耳に馴染まないフレーズが多すぎる。無理やり歌詞を乗せてるように思える部分が多い。(字余りな状態)
製作に丸2年の月日を費やしたそうだが、70年代と比べてもテクノロジーの進化、自前のスタジオ、RIVER SOUNDでの録音、という点を考えると、やはり途方もない時間をかけた作品だといえる。
ドラマーを6人も起用してる点に相変わらずのこだわり具合が垣間見れるものの、以前のような豪勢なミュージシャン達をかき集めてサウンドを構築して行くようなやり方は取られていないらしい。クレジットされたミュージシャンの数は物足りない程少ない。(が、実際のセッションがどうだったのかは定かではない。)
後期の作品で見られた、セッションに参加したミュージシャンのアイディアを借りながら曲を完成させて行く、というプロセスは今作では殆どなかったようだ。二人のアイディアだけで曲を作った事が原因とすると、GARY KATZの不在がその意味で影響したのかもしれない。
カバーのアートワークも妙にのどかなもので、裏ジャケにいたっては、ガーデン小物と、ますます意味不明だが、スタジオに篭りっきりで身を削って作られた以前の作品と比べると、リラックスして作られたという様子が伝わってくる。
結局生みの苦しみの分の緊張感がマイナスされたという事だろうか。"Home At Last"のイントロとか、"Aja"のドラムソロ、"Third World Man"のギターソロの様に、最初に聴いた時にピピッと来て、その後何百回聴いても良い、大袈裟に言うと、心に染み込むような部分が今作は殆どない。実験的な部分が多く、歌詞で冒険してる点といい、初期〜中期の作品に似ている。特にギターの復権がその象徴のようだ。
BECKERのギターがカッコ良かったのは嬉しい誤算だったが、逆にゲストミュージシャンが少ないという弊害?も生じた。
AJAはFAGEN・BECKERのコラボレーションの最高峰だと思うので、BECKERの重要性が認識されたという意味でも今作は良いステップだったはず。次作に大いに期待します。